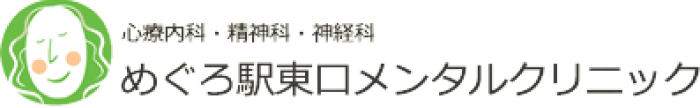感性の歴史① A・コルバン「においの歴史」
感性の革命――
アラン・コルバン『においの歴史』が解き明かす「不快感」の正体

私たちの「鼻」は、私たちが思うほど自由ではありません。
現代の日本社会において、私たちは「清潔であること」に異常なほどの情熱を注いでいます。しかし、歴史学者のアラン・コルバンが解き明かしたのは、こうした「不快感」が本能ではなく、社会や文化によって巧みに作り上げられてきたという事実でした。私たちの鼻は、歴史の中で「教育」されてきたのです。
序章:かつて、悪臭は「生」の一部だった
18世紀半ばまでのヨーロッパでは、においは風景の一部であり、生活の活気そのものでした。コルバンは、ある時期を境に人々がにおいを排除し始めた変化を「嗅覚の革命」と呼びました。それは、人間が世界を認識する「感性」そのものが根底から覆った瞬間だったのです。
1. 瘴気(ミアズマ)の恐怖:においが「死」を運ぶ時代
18世紀、有機物の腐敗から立ち上る悪臭(瘴気)が病気を運ぶという「瘴気説」が信じられていました。「におう」ことは「死がそこにある」ことを意味し、市民の生命を脅かす毒と見なされました。
- 都市の換気: 墓地の郊外移転や下水道の整備が進められました。
- 空間の改造: 病院や刑務所の脱臭が公衆衛生の至上命令となりました。
2. 科学の光と「過敏な英雄」の誕生
18世紀後半、科学の進歩により「生活のにおい」は科学的な不純物として意識され始めます。洗練されたエリート層ほど、わずかな刺激にも反応する「繊細な神経」を持つことがステータスとなりました。
- 香水の変化: 濃厚な動物性香料は嫌われ、清潔さを象徴する植物性の香りが洗練の証となりました。
3. 階級という「見えない壁」を築くにおい
19世紀の中産階級は、自らを「無臭」と定義し、労働者層を「悪臭を放つ群れ」として描き出すことで優越性を確立しようとしました。排泄が個室へと隠され、自分のにおいを他人に嗅がせないことが近代市民のマナーとなったのです。
4. 記憶と内面:香りが「私」を語り始める
脱臭された世界では、かすかな香りが際立つようになります。ボードレールやプルーストの文学に見られるように、香りは過去の記憶や感情を呼び覚ます「記憶の触媒」としての役割を担うようになりました。
結論:私たちが「無臭」の先に失ったもの
アラン・コルバンが突きつけたのは、「あなたの『不快』という感覚は、本当にあなた自身のものか?」という問いです。
- 1. 感覚の歴史性: 不快感は医学、科学、階級支配の文脈で「教育」されたものである。
- 2. 空間の変容: 都市や住居は、当時の人々が「鼻」で感じた恐怖や欲望の具現化である。
- 3. 権力の嗅覚: 嗅覚は人々を分断するための強力なツールとして機能してきた。
歴史が作り上げた「感性のフィルター」を意識してみること。それが、コルバンの描いた感性の世界を理解する第一歩です。